自己負担割合について
保険証の自己負担割合について
お医者さんにかかるとき
病気やケガをしたときは、医療機関や保険薬局の窓口でマイナ保険証または資格確認書を提示すれば、年齢等に応じた自己負担割合(下記参照)を支払うだけで、次のような医療を受けられます。
診察、在宅療養、入院、薬や治療材料の支給、医療処置・手術などの治療、訪問介護
(医師が必要ないと判断するものは、国保では扱えません。)
| 義務教育就学前 | 2割 | |
| 義務教育就学後 70歳未満 |
3割 | |
| 70歳以上75歳未満 | 2割 | |
| 3割 | 現役並み所得者 | |
70歳以上75歳未満の方の高齢受給者証について
紙の保険証の廃止により、「高齢受給者証」の新規発行が廃止となります。12月1日時点でお手元にある有効な「高齢受給者証」は、住所や負担区分等に変更がなければ、有効期限の令和7年7月31日までお使いいただけます。医療機関や保険薬局では保険証兼高齢受給者証を提出してください。
現役並み所得者
3割負担になる方は、同一世帯に住民税課税所得※が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険被保険者がいる場合です。
ただし、住民税課税所得※による判定で3割負担になる方でも、下記の(1)(2)(3)に該当する方については、申請により、「一般」の区分と同様となります。
※調整控除が適用される場合は控除後の金額になります。
| 同一世帯の70歳以上75歳未満の国保被保険者数 | 収入合計額 | |
| (1) | 1人 | 383万円未満 |
| (2) | 後期高齢者医療制度への移行で国保を抜けた人を含めて合計520万円未満 | |
| (3) | 2人以上 | 合計520万円未満 |
- 昭和20年1月2日以降生まれで70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる世帯のうち、70歳以上75歳未満の国保被保険者の「基礎控除後の総所得金額等」の合計額が210万円以下の場合は「一般」の区分と同様となります。この場合は申請は不要です。
- 所得金額でなく収入金額です。必要経費、各種控除、損益通算により所得が0円またはマイナスになる場合でも、収入金額としてはプラスの金額が生じることとなります。
※株式等に係る譲渡所得等の金額を申告分離課税分として申告する場合、ここでいう収入金額は、株式の譲渡益ではなく、売却代金となります。よって、株式譲渡益がマイナスになったことにより、損失等の申告をする場合、収入金額としてはプラスの金額が生じるため、医療費の自己負担割合が3割負担のままとなる可能性があります。
一般
現役並み所得者、低所得者2、低所得者1以外の方
低所得者2
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1を除く)
低所得者1
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
世帯で見る負担割合の例
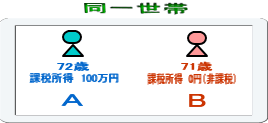
A・・・2割負担
B・・・2割負担
ともに課税所得が145万円未満のため
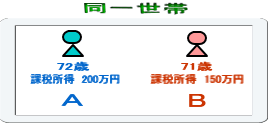
A・・・3割負担
B・・・3割負担
ともに課税所得が145万円以上のため
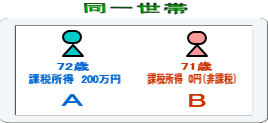
A・・・3割負担
B・・・3割負担
Aは145万円以上のため3割負担。
Bも課税所得は0円だが、同一世帯に145万円以上ある70歳以上の方がいるため。
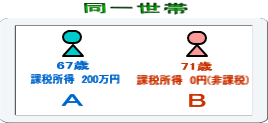
A・・・高齢受給者証交付対象者ではありません
B・・・2割負担
同一世帯に145万円以上の課税所得者がいるが、70歳以下なので判定対象にはならないため。
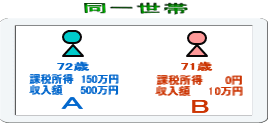
(基準収入額適用申請書の提出により)
A・・・3割負担が2割負担になります
B・・・3割負担が2割負担になります
課税所得での判定では、3割負担だが収入額が合計で520万円未満のため、基準収入額適用申請書の提出により負担割合が変更される。
この記事に関するお問い合わせ先
生活部 保険課
業務時間:午前8時45分~午後5時30分
〒666-0292
兵庫県川辺郡猪名川町上野字北畑11-1
電話:072-767-6235
ファックス:072-767-7200





更新日:2026年01月15日